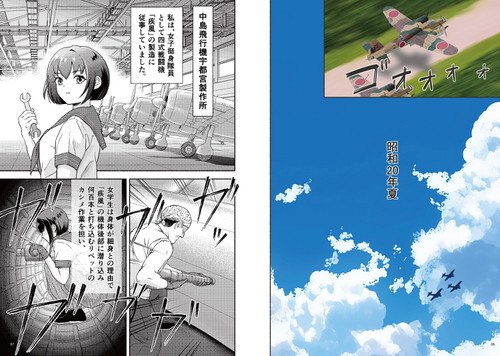正月十四日(ノンフィクション短編小説)
正月十四日。
境内には冷たい空気と反して、お焚き上げの炎が勢いよく燃えていた。
どんど焼きは、去年一年の願いを天に返す日だ。
私はその火のそばで、人々から縁起物を受け取っていた。
古い破魔矢、色あせたお守り、少し傾いたしめ飾り。
どれもが、誰かの思いをまとっている。
そのとき、笑い声と足音が境内に弾けるように響いた。
近所の女子高のジャージ姿の女子高生が五人。
真冬だというのにハーフパンツで、褐色の肌がまぶしいほどだった。
胸に抱えているのは、大きなだるまだ。
「お願いします!」
差し出されただるまは、ずしりと重かった。
私はそれを火の中へ、そっと入れる。五人の見つめる中、
炎が一気に燃え上がった。
「あーーー! 燃える燃える!」
歓声とも、嗚咽ともつかない声が上がった。
誰かが一瞬、唇を噛んだのが見えた。
「インターハイ出場」と書かれた、片目のままのだるまは、
ゆっくりと灰に崩れ、やがて見えなくなった。